えくぼ先生6時間目
ドライポイントと彩色による身の回りの静物画
drypoints
画像をクリックすると大きな画面で見れます
|
|
えくぼ先生の参考作品 |
|
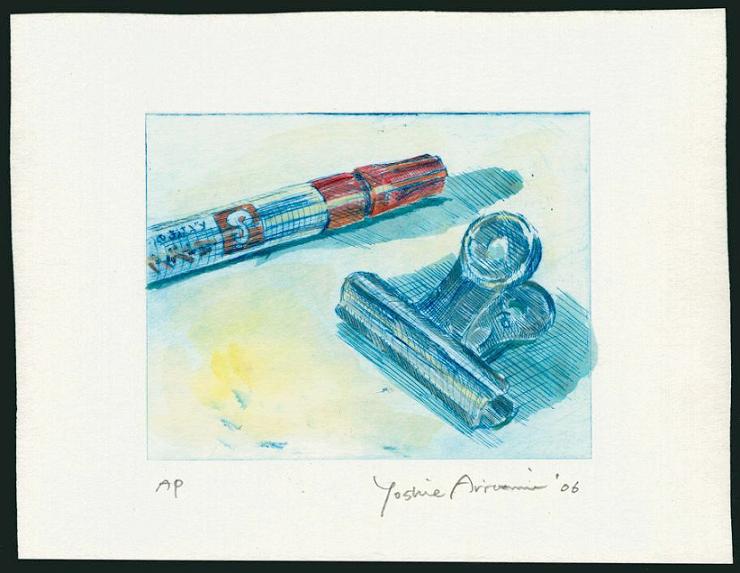
|
|
制作の進め方 |
|
1、静物の前に透明の塩ビ板(アクリル板)をおき、上から油性ペンで静物や影の形をなぞる。
2、なぞったものをもとに、ニードルで塩ビ板を削っていく。
3、塩ビ版にインクをのせ、ふき取り、プレス機で刷る。
4、すったものに水彩絵の具で彩色する。
|
|
えくぼせんせいのコメント
|
|
・ドライポイントは、金属の針(ニードル)を使い、版(一般的に銅板、この場合塩ビ板)に直接彫って描画する版画の技法(凹版技法)です。削ったところが黒の線として出ます。黒い(灰色い)広い面を出したいときは、線を網目状に彫っていきます。
・静物の上に塩ビ板を置くとき、斜めに置いて、なぞらせたよ。
・彩色は、簡単に。そのかわり、影(明暗)や形をしっかり、版に彫っておいたほうがいいわ。(彩色しなくても白黒の作品になるくらい。)
|
|
生徒作品 |
|
  
|
|
メガネ先生の授業の裏を読む |
|
写実的な表現ができるこの方法は、モチーフの選び方や作る目的が大事になってきます。(写真に負けないものが必要になります。)身近なものを原寸大で表現させたこの教材は、身近なものを普段と違う角度から見つめなすことができた点で、よいモチーフ選びをしたのではないかと思います。
細かい葉脈の葉などもモチーフとしては面白いと思います。
モチーフを変えることで、小学生くらいの子供には細かいところまで写し取る面白さを、大人にはモチーフと構図の妙と対象の再発見を楽しめるものになるでしょう。
|